こんにちは、ゆうです。
元会計事務所職員です。
この記事を開いていただき、ありがとうございます。
経理業務は企業規模の拡大とともに着実に増えていくものです。
・「今までのやり方では回らない」
・「顧問料が高くなってきた」
という状況は、多くの中小企業で共通して起こります。
今回は、税理士任せから一歩進み、経理を効率化しながらコストも抑える方法をご紹介します。
- 事業成長中の中小企業で経理を兼任している社長
本記事の信頼性

企業の成長とともに経理業務は必ず増える

私は会計事務所職員のころ、顧問先の企業のもとに訪問しては領収書や預金通帳等をお預かりし、記帳代行をしていました。
順調に成長している企業の悩みのひとつ、、、
会社の売上や取引先が増えると、経理の仕訳数が確実に増えます。
- 売上伝票、仕入伝票が増える
- 経費精算や交通費精算が増える
- 人件費・賞与・社会保険の処理が増える
- 固定資産や減価償却の処理も増える
年商1億円から3億円に成長すれば、仕訳数が増えるのは普通です。
そして、それに比例して税理士の顧問料も増える傾向があります。
顧問料は「作業量」と比例する
税理士の顧問料は、以下の要素で決まるのが一般的です。
- 年商規模
- 取引件数(仕訳数)
- 記帳代行の有無
- 訪問回数やサポート内容
取引が増えれば、税理士事務所での作業時間も増えるため、顧問料の引き上げは避けられません。
これは企業の成長に伴う自然な現象といえます。
税理士に内製化を進められる

税理士から「記帳は社内でやってみませんか?」と提案されるのもよくある話です。
税理士としては、仕訳の入力業務は経理担当者やパートスタッフに任せてもらい、より専門性の高い申告や節税提案に時間を使いたいと考えます。
顧問料を抑えたい企業側と、作業負担を減らしたい税理士側の利害が一致するため、企業の成長に伴い内製化が勧められるのは自然です。
クラウド会計ソフトの普及により、仕訳入力や領収書管理もオンラインで完結できるようになった今、内製化のハードル自体も下がってきています。
私が勤めていた会計事務所では、小規模な会社が多く、記帳代行も受けるケースが大半でしたが、
規模が大きく体力のあるクライアントは自社に経理機能が存在し、記帳は内製化されていました。
では記帳代行は内製化する?選択肢は4つ
内製化をすべきかどうかは、会社の状況によって考えるのがよいでしょう。
選択肢は4つです。
内製化
1. 自社スタッフ(内製化)
メリット 記帳代行に限らず業務をしてもらえる
デメリット スキルは個人によってばらつきがある。退職した場合は教育しなおし。
外注
2. 税理士(継続)
メリット 記帳から税務申告までワンストップ(手間が省ける)
デメリット 費用が高め
3. 記帳代行会社
メリット 税理士より低価格
デメリット フリーランスよりは割高
4. 実務経験のあるフリーランス
メリット 安価で専門性も確保できる
デメリット 情報漏洩の懸念
外注|実務経験のあるフリーランスへの依頼

近年、クラウドワークス、ランサーズ、ココナラなどで実力のある実務経験者に依頼をすることが一般化しました。
実務経験豊富な以下のような人材が多数登録しており、フリーランスの方にオンラインで依頼できます。
- 元経理担当者(上場企業や中小企業経験者)
- 元会計事務所スタッフ
- 日商簿記2級・1級、税理士科目合格者
依頼可能な業務例:
- 仕訳入力(会計ソフト使用)
- 請求書作成
- 経費精算処理
- 領収書・証憑整理
フリーランスへの委託は定期契約でウィンウィンの関係に
外部の経理人材に定期的な契約で依頼することで、次のようなメリットが生まれます。
企業側のメリット
- 人件費を変動費化できる(雇用リスク軽減)
- 必要な時だけ仕事を依頼できる
- 顧問料を抑えられる
フリーランス側のメリット
- 安定した収入源を確保できる
- 長期契約で信頼関係を築ける
- 複数クライアントを掛け持ちできる
お互いの利害が一致するため、継続的に良好な関係を築きやすいのが特徴です。
「顧問料が高い」と感じている場合も、経理経験者を検索することで解決につながります。
まとめ
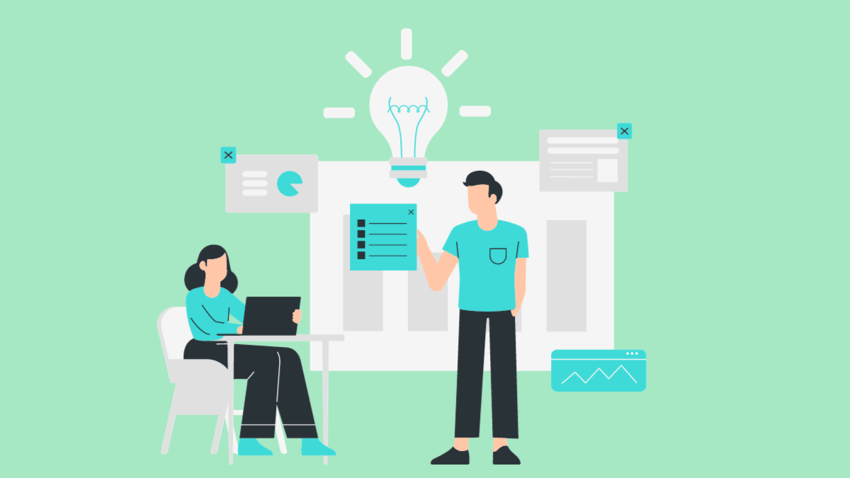
中小企業が成長すると、経理業務は必ず増えます。
税理士任せにせず、必要に応じて外部の実務経験者に依頼することで、顧問料や人件費を抑えながら経理を効率化できます。
- 仕訳数の増加 → 顧問料アップは避けられない
- オンライン外注 → 経理人材を柔軟に確保
- 定期契約 → 双方にメリット
経理体制の見直しは、会社の成長とともに必要になる「経営戦略の一部」です。
いまはコストを抑えつつ専門性を確保するのが最適解かもしれません。
企業の成長フェーズに合わせて、体制を整えていきましょう。

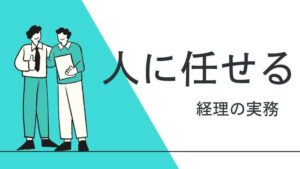
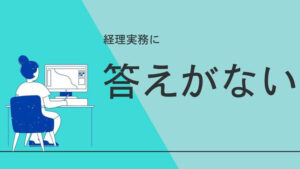
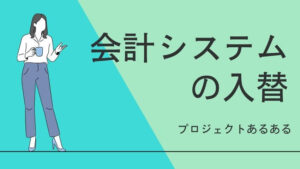

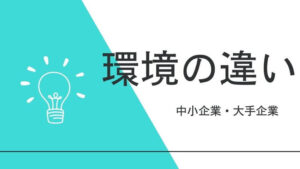

コメント