こんにちは、ゆうです。
大手上場企業の経理部でマネージャーをやっています。
この記事を開いていただき、ありがとうございます。
「会計の勉強は頑張ってきた。でも実務経験はない。」
そんな状態で経理の仕事に飛び込むと、最初にぶつかる壁があります。
それは――
「経理の仕事には答えがあるはずだ」という先入観です。
学生時代に簿記を学んだ方、資格試験に取り組んできた方ほど、この感覚にとらわれやすいものです。テキストには常に正解があり、過去問には必ず模範解答がありました。
でも、実際の経理の現場では違います。
あなたの職場にいる優秀な経理パーソンも、必ず持っている考え方。
この記事を読めば、若手経理パーソンが早めに知っておきたい「経理実務に必要な思考法」を身に付けることができます。
- 若手経理パーソン
- 担当業務の面倒すぎるルールに苦しんでいる経理パーソン
- 経理実務のコツを知りたい方
本記事の信頼性

実務には「答えがない」ことが多い

どんな仕事も同じですが、経理の世界にも答えがないことが山ほどあります。
例えばこんな場面です。
・ 経費精算のルール 「未払計上は何円以上にする?」
→ 会社によってバラバラ。
・ 使用科目の判断 「この取引は何の科目にする?」
→ 根拠基準、金額規模、発生の継続性など、人によって見解が分かれる。
・ 開示対象範囲 「この情報は開示する?しない?」
→ 開示ルールに記載の用語について明確な定義がなく、開示は任意。なんてことも
会計基準の文言だけでは白黒つかない。
調べても調べても、教科書的な“正解”は見つかりません。
むしろ 「決める」ことが仕事 になるのです。
答えは「探す」のではなく「決める」
経理において重要なのは、答えを探す姿勢ではなく、答えを整理して決める力です。
このとき必要なのは「理屈を説明できるかどうか」。
- どの会計基準を根拠として判断したのか?
- 何をもって重要性が低いと判断したのか?
- 誰と相談して、どのような合意を得たのか?
こうした整理を言語化できることが、経理パーソンとしての腕の見せどころ。
「決める」という発想を持てれば、
- 意思決定につなげられる人
- 業務量を減らせる人
になれます。
答えを「決める」ときの基本の流れ

優秀な経理パーソンは、答えのない問題に対して以下のプロセスで解決していきます。
情報収集 → 情報整理(選択肢候補別など) → 方針案作成 → 提案 → 決定
情報整理までは、会計基準などの「知識」が活きますが、逆に「知識」があっても結論まで導くことはできません。
基本的には、関係者の合意を得ながら決定していきます。
- 直属の上司や役員
- 関連部署のキーパーソン
- 監査法人
自分ひとりでは答えは出せないのです。
経理という職種が「専門性」に加え「コミュニケーション能力」を求められる背景でもあります。
判断のコツは「重要性」と「ルール化」
経理は属人的に処理をしてしまうと、後から混乱が生じます。
だからこそ、ルール化が大事。
- 数値基準を決める(例:総資産の1%、10億円以上は開示など)
- 継続的に発生する取引は処理方針を固める
- 監査法人とすり合わせて議事録を残す
- 一度決めたらブレないように継続する
重要性の線引き(数値基準)は、ちょっと大胆なくらいが効果があります。
(もちろん会計基準や自社の会計方針を守ることは前提で)
既存の担当業務が細かすぎると感じている方は、過去の整理が細かすぎるケースもあるかもしれません。(整理されたことがない。という場合も普通にありえます)
べき論で処理するのは安心はしますが、本当に時間を割くべき重要な業務はほかにあるはず。
必要に応じて処理しない範囲をルール化し、業務を見直していきましょう。
これらができるようになると
- 重要性の低い業務の廃止
- 議論や意思決定回数の削減(ルールに基づく機械的な処理)
となり、
この積み重ねが、効率化にもつながります。
提案型のコミュニケーションで価値は高まる

経理現場における提案型コミュニケーション
提案型のコミュニケーションがとれる経理パーソンは出世や年収アップにつながります。
「提案できる人」は答えのない問題について、「方針を決める人」になっていくからです。
私は日常的に若手経理スタッフから相談を受けるのですが、2パターンあります。
- どうすればよいですか?
- 私はこう考えますがいかがでしょうか?
後者であれば、提案型です。
上司としては基本的にYesかNoで答えることになります。
考え方に大きなズレがなければ、「方針を決める判断力」があるとみなして、少しずつ大きな仕事や裁量を持った仕事を任せていきます。
意思決定者を目指した訓練となる
若手のころは、まず自分なりの意見を持つ。ということから始めてみてください。
(間違えていようが気にしてはいけません。)
自分なりの意見を持つことで、上司と部下は、
「教える」「教わる」の関係から、「議論しあえる関係」へと発展していきます。
日ごろから理由と結論を用意し、提案型のコミュニケーションをとることをおススメします。
それが答えのない問題に対して「決める」訓練を重ねることとなり、
自然と経理のキャリアアップにつながっていきます。
まとめ:先入観を捨てると成長が早い
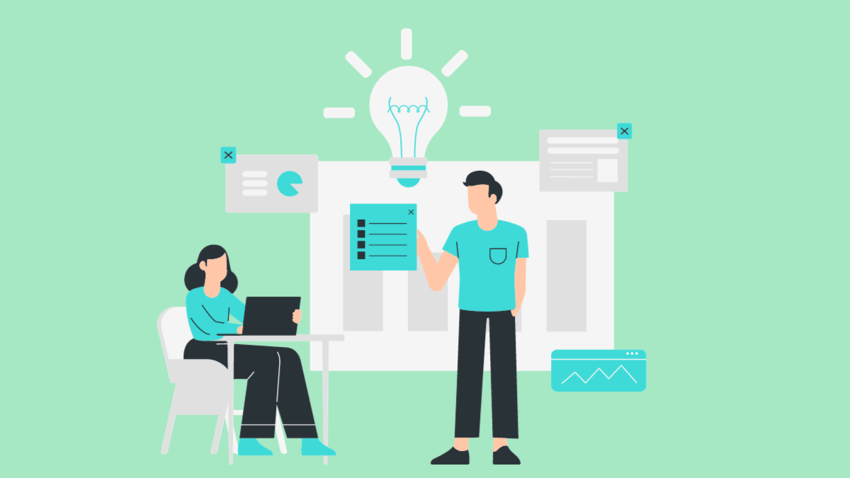
経理の世界は「答えを探す仕事」ではなく「答えを決める仕事」です。
理屈をもって整理し、社内や外部専門家と共有のうえ、決定する――。
これができると、仕事の迷いが減り、効率的に進められるようになります。
ぜひ、「答えは決めるもの」という視点を持ってみてください。
明日から仕事の進め方が変わるかもしれません。

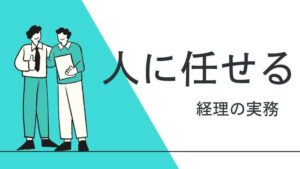
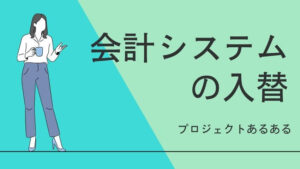


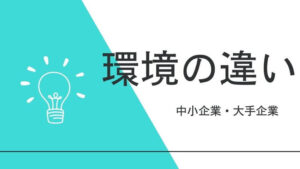


コメント