こんにちは、ゆうです。
大手上場企業の経理部でマネジャーをやっています。
この記事を開いていただき、ありがとうございます。
連結決算を担当している皆さんなら、一度は感じたことがあるのではないでしょうか。
「子会社の経理担当者によって、連結決算業務は天国にも地獄にもなる」
これは、私が連結決算を担当してきた中で、何度も実感したリアルな真理です。
今回は、子会社の規模や担当者の力量がどのように親会社の業務に影響するのか、そして実際に起きた課題とその改善策についてご紹介します。
- 連結決算の実務を知りたい方
- 経理部に所属する連結決算担当者
- 子会社の経理担当者
本記事の信頼性

子会社の経理力に左右される親会社の運命
連結決算においては、子会社が作成する連結パッケージの「提出スピード」と「品質」が非常に重要です。
子会社の規模や体制によって、連結パッケージの状況は異なります。
- 大規模な子会社は、処理量が多く複雑ですが、経理担当者のスキルも高い傾向にあり、精度も高い。
- 小規模な子会社は、処理内容自体が単純で、誤りがあっても親会社側で早期に修正可能です。
しかし問題なのは、上記以外。
「それなりに規模があるのに、経理担当者の知見が不足している」というケースです。
ここが、最も注意を要する“落とし穴”です。
実録:連結決算の現場で起きた課題
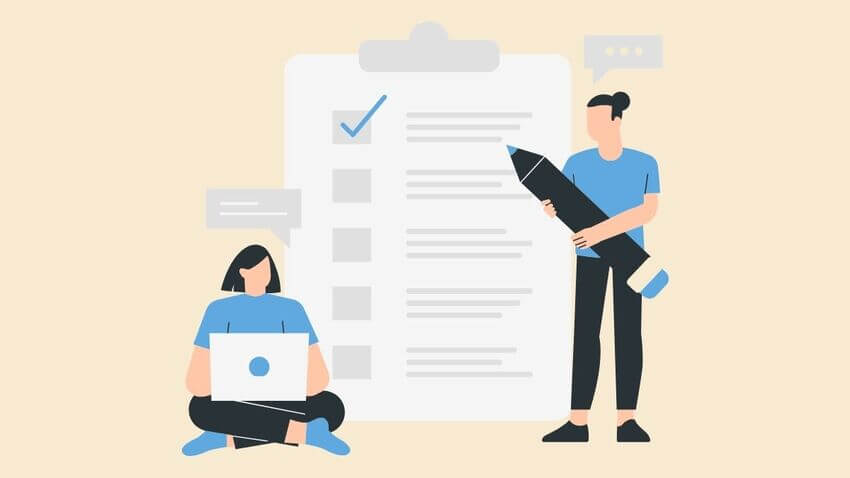
あるケースでは、5社の子会社連結パッケージをたった1人の担当者が抱えていました。
会社の施策でM&Aにより子会社の子会社(いわゆる孫会社)が増加した結果1人で5社を担当されていました。
その方の置かれている立場上、5社の連結パッケージを1人で作成するのは困難でした。
(私も子会社のことなので、容易に口出しできる立場でもありませんでした。)
その結果、次のような問題が発生していました。
- 提出の遅延が常態化
- 貸借不一致や残高の不整合
- 同じミスの繰り返し
- 資料提出漏れ
- メールに返信が来ない
こうしたミスが親会社にどんな影響を及ぼすかというと…
- 連結作業の遅延
- パッケージチェック→差し戻し→再提出のラリーの連続
- 連結決算スケジュールの圧迫

連結決算業務の改善提言
では、どうすればこの“地獄”から脱出できるのでしょうか。
現場の経験をもとに、子会社側にお願いしたい改善ポイントを以下にまとめました。
決算体制の強化
担当者の人数を増やす、または知見のある人材を配置
1人でできることには限界がありますが、人数が増えれば解決することがあります。
逆に経験の浅い人を増やしても立ちいかない場合もあるでしょう。
その場合、知見のある人材を配置したいところです。
私の経験上、担当者のミスが多く悩みのタネだった子会社について
凄腕の経理パーソンへの担当変更により劇的に改善したことがあります。
- コミュニケーションが円滑
- 正確な処理
- 作業スピードが早い
- 資料が見やすい
子会社担当者が知見のある人に変わることで、親会社の職場環境まで良い影響があり感動しました。
上層部の理解と支援を促す
決算体制の強化は、人員不足の解消などリソースの問題に行き着くことも多いです。
特に事業拡大中の子会社では、会社の成長スピードに対してコーポレート部門が置いてけぼりになりがちです。
管掌役員クラスが経理現場を放置しすぎず、適度な距離感で状況を把握しているとよいのですが。
必要に応じて、権限のある方に理解と支援を促す必要もあるでしょう。
その場合、以下のように客観性のある情報を整理しておくことがポイントです。
- 実際に起きた「遅延」や「ミス」の内容
- 同規模他社での経理人員数(参考情報として)
提出スピードの向上
提出期限の厳守
連結パッケージの提出期日に間に合わないと、連結決算スケジュールの遅延に影響します。
困難と思われる場合
- 要因の特定と対策
- 提出が間に合うものとそうでないものの分離(一部でも先に提出)
最大限、期限に間に合わせるように調整しつつ、
障壁となっている部分については次への課題として段階的に解決していくことも重要です。
修正時のレスポンス
連結パッケージは提出後の親会社側のチェックと差し戻しにより、子会社側での修正が必要となるケースもあります。
このとき子会社側のレスポンスが遅いと、連結決算遅延につながるため、連結パッケージ提出後もしばらく気を抜かないように注意が必要です。
提出資料の確認と整合性の徹底
提出漏れチェックリストの活用
子会社から親会社に提出する資料やファイルは複数にわたります。
提出漏れがあると、双方でコミュニケーションコストも発生するので事前確認したうえでの提出が大切です。
整合性の確認
連結パッケージの入力誤りの例として
- BS貸借の一致
- SSの期首残高と前期末残高の一致
- 注記情報の入力漏れ
- 数値の更新漏れ
などがあります。
検証機能を連結パッケージに組み込むなど、親会社側での仕組み化も大切ですが、
子会社側でも連結パッケージ入力後にチェックの徹底を実施したいものです。
必要ならば経営層に申し出る
状況によっては、経理の担当者レベルを超えた話しになることもあります。
私も子会社の役員クラスの方に直接改善の申し入れをすることもしばしばありました。
非常に緊張する場面ですが、
- 子会社の経理部門がどのような状況にあるか。
- また、連結決算にどのように影響しているのか。
現状を認識していただき、決算体制整備の推進が必要であることを理解していただきます。
親会社側の取り組み

もちろん、親会社側も手をこまねいているわけではありません。
やるべきことがあります。
決算事前ミーティングの開催
子会社との情報共有やすり合わせの場があると、決算時にスムーズになります。
特にイレギュラーな論点が発生する場合は、開催するようにしています。
- どういう論点があるか
- リストどのような処理方法があって、どういう方針にするか
- 親会社と子会社のタスクはどう分けるか
- 重要性の観点から子会社の作業負担を減らせることがないか。
親会社側の判断で子会社の負担を軽減できることもあります。
子会社の体制強化をサポートする提言活動
子会社で「設立」「取得」「合併」などが行われる場合、
親会社側でもその件につき、「取締役会資料」「決裁書」「稟議書」などが経理部門にまわってきます。
その際は、コーポレート部門の体制整備が盛り込まれているか
問題が起きる前に子会社決算体制について提言するのも親会社経理の仕事です。
グループ全体での決算教育の実施
例えば、連結パッケージの入力方法の説明会を開催するなど
子会社に対して必要なサポートを提供することも、親会社の取り組みのひとつです。
最近は簡単に画面録画等もできるので、説明動画の配布というやり方もありますね。
システム面の改善(連結会計システムの入替)
大きなテーマではありますが、連結会計システムの導入や入替により子会社の負担を低減することは可能です。
親会社の立場からすると、子会社には日ごろからお願いすることばかりです。
連結決算の仕組みを会計システムの機能により根本的に変える。
その成果を子会社に還元できたときは、親会社としても胸を張れる瞬間になるでしょう。
最後に:連結決算は「チームプレー」

連結決算は、単なる数字の集計作業ではありません。
子会社と親会社の連携、協力、意識共有があってこそ、正確かつスピーディな決算が実現します。
一人ひとりが“自分ごと”として取り組むことが、最終的にグループ全体のガバナンス強化につながるのです。

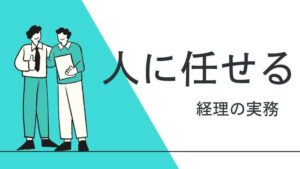
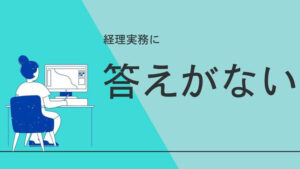
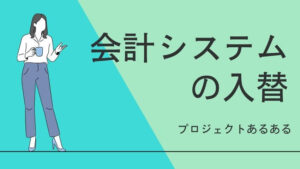


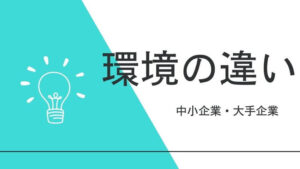

コメント